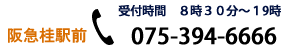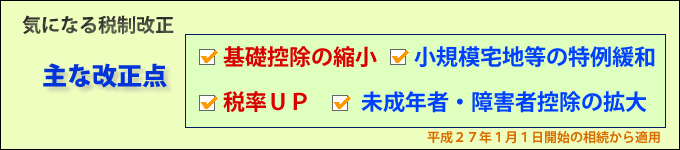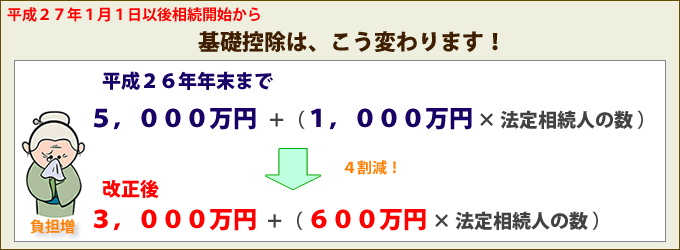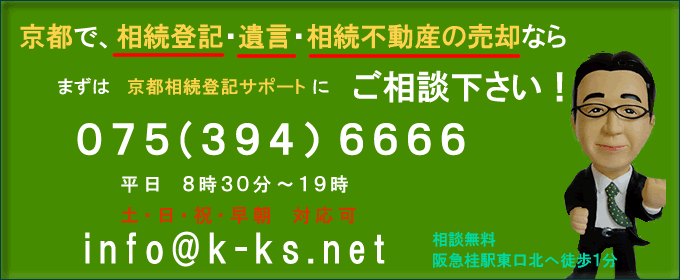- HOME
- >
- 気になる税制改正
気になる税制改正
新税制の主な改正点
平成27年1月から相続税の制度改正がなされる結果、財務省の試算によると、相続税を納税する人が、現在の4%から、6%程度にまで増加すると考えられています。
そのなかでも、特に影響が大きいのが、基礎控除の縮小をはじめ、以下の4項目であるといわれています。
税制改正その1. 基礎控除の縮小(強化)
基礎控除が4割も減る!
相続税法における基礎控除とは、相続税を計算する際に、各人の課税価格の合計額から差し引くことができる非課税枠のことです。
課税される遺産総額が少なければ、それだけ相続税の負担が少なくなるため、基礎控除が縮小されると、それだけ、納税者の負担が増えるといえます。
しかも、その縮小幅が、かなり大きく、実に4割も減ることとなります。
この結果、都心部で持ち家がある家庭では、預貯金等他の金融資産が少なくても、納税が必要なケースが出てくると言われいます。
基礎控除縮小による具体的影響
例えば、夫が死亡し、相続人が3名(妻と子2名)、相続財産の総額が8千万円のケースを考えてみます。(他の控除・特例等は考慮しないものとします。)
平成26年年末迄に相続開始する場合(以下、「旧法」という。)では、基礎控除は8千万円となり、相続税はかかりません。
対して、平成27年1月1日以降に相続が開始する場合(以下、「新法」という。)では、基礎控除が4千8百万円に減るため、差額3千2百万円に相続税がかかることになります。
税制改正その2. 税率UP!(強化)
相続税の超過累進税率の構造が変わり、一部で税率が上がります
各法定相続人の取得金額が2億円を超えるところから、税率が上がる(最高税率50%から55%に)ことになります。
富裕層を対象とする課税強化ですが、基礎控除の縮小と共に、相続税の増税と言われる所以となっています。
税制改正その3. 小規模宅地等の特例の適用範囲拡大(緩和)
1.そもそも、小規模宅地等の特例とは
相続財産中、自宅の土地(宅地)の評価額を、一定の面積に限り、8割減額(つまり2割に)する、という特例のことです。
相続財産の中でも特に不動産は、評価によって、遺産総額を大きく押し上げる場合があり、この特例が使えるか否かは、不動産を持つ家庭にとって、大きな影響があるので、きちんと使えるようにしておくことが、重要な相続対策となります。
2.限度面積の拡大
限度面積が、旧法220㎡から新法330㎡に拡大されます。
3.特定事業用宅地等も限度面積拡大
旧法では、自宅用と事業用の土地両方を相続する場合には、調整して400㎡が限度で、両方合算した640㎡までを特例適用することはできませんでしたが、新法では、両方合算した最高730㎡(自宅330㎡+事業要400㎡)まで、特例適用面積が拡大されることになります。
4.適用要件の緩和(既に平成26年1月1日相続開始分から適用済)
二世帯住宅に居住していたり、老人ホーム等に入居・入所していた場合の特例適用が緩和されました。
具体的には、中で行き来できない完全分離の二世帯住宅も対象となったり(但し相続開始時に相続人が自宅居住必須)、所有権付老人ホームに居住していても(但し自宅を賃貸していてはダメ)適用が受けられるようになりました。
この緩和措置は、平成26年1月1日から、既に適用となっています。
税制改正その4. 未成年者控除・障害者控除の引き上げ(緩和)
旧法からある特別控除たる未成年者控除(20歳まで)と障害者控除(85歳まで)について、それぞれにつき年4万円づつ(旧法では年6万円が、新法では年10万円に、特別障害者は年20万円)、控除額が引き上げられます。
税制改正その5. 贈与(暦年課税)の緩和と強化
1.贈与税率の一部が引き上げられました(強化)
旧法で、最高税率50%であったものが、新法では55%に引き上げられると共に、基礎控除後の課税価格が1千万円超の贈与については、税率が引き上げられました。
2.直系尊属から、子や孫への贈与は税率が引き下げられました(緩和)
前項で税率が引き上げられた部分がある一方で、直系尊属(父母や祖父母)から、20歳以上の子や孫への贈与に限り、新しい税率表が適用されることとなり、贈与税率が引き下げられています。(さらに、教育資金の一括贈与非課税措置も注目です。)
税制改正その6. 贈与(相続時精算課税)の緩和
1.受贈者の対象が孫にも拡大(緩和)
旧法では、贈与の対象が子だけでしたが、新法からは、孫にも適用されることになりました。
2.贈与者の年齢が引き下げに(緩和)
旧法では、贈与者は、65歳以上(贈与の年の1月1日現在で)とされていましたが、新法では、60歳以上に引き下げられました。