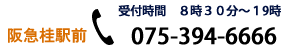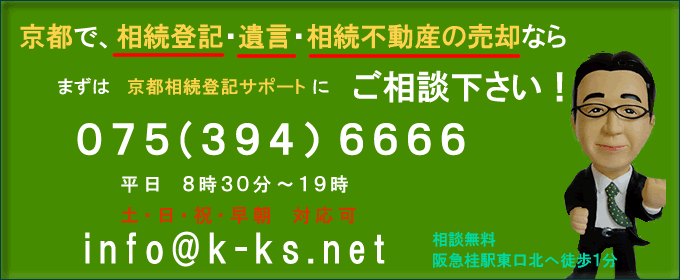成年後見開始の申立・後見人就任
法定後見人(成年後見人)職務開始までの流れ

後見開始審判申立てができる人(申立権者)
本人(申立能力がある場合)、配偶者、四親等内親族、保佐人、補助人、任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人、市区町村長、検察官、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐監督人、補助監督人
後見開始の審判申立てをする家庭裁判所(管轄)
本人の住所地の家庭裁判所
提出書類
1.申立書(800円収入印紙貼)
2.収入印紙2,600円・予納切手3,090円(平成26年4月現在)
3.本人の戸籍謄本・住民票(省略なし)
4.四親等内親族の申立の場合、現在戸籍謄本
(さらに、確認のため、つながりのわかる戸・除籍謄本等も)
5.候補者の住民票・身分証明書・照会書
6.本人の後見等が登記されていないことの証明書(特定の様式あり)
7.医師の診断書(特定の様式あり)
8.本人の照会書
9.親族関係図
10.不動産の登記事項証明書及び固定資産税評価証明書
11.収入・支出・負債に関する資料
12.預貯金、株式、保険等金融資産に関する資料
13.その他必要に応じ手配、作成
成年後見人就任
成年後見人となる者
欠格事由(未成年者・破産者等)に該当しないことは勿論、成年後見人として、他人の財産を管理できる能力や倫理感(不正を働かないか)が備わっているかを、家庭裁判所は総合的に判断して、決めます。
申立て時に、候補者を立てることもできますし、適当な候補者がいない場合には、審判時に、家庭裁判所がふさわしい人を選任します。
申立て時に親族の候補者を立てたとしても、高度な法律行為が必要な案件の場合や、親族間でトラブルになりそうな場合には、司法書士等の法律専門職が選任されることがあります。
成年後見人の義務と権限
本人の意思を尊重し、身上に配慮する義務があります。
また、財産に関する法律行為について、包括的な代理権と財産管理権、取消権があります。
但し、以下の行為は、成年後見人でもすることができません。
1.日常生活に必要な範囲の行為についての取消
2.一身専属的行為(遺言・認知・婚姻等)
3.居住用不動産の勝手な(家裁の許可ない)処分
成年後見監督人
家庭裁判所が必要と認めるときに、成年後見人を監督する成年後見監督人を選任することがあります。
親族が成年後見人となる場合に、司法書士等の法律専門職が、成年後見監督人となることもあります。
後見人による被後見人の居住用不動産の処分
被後見人の居住用の不動産を処分(売却・担保設定等)する際には、事前に家庭裁判所の許可を得なければなりません。
万一、許可なく売買代金の授受を行って、物件を引き渡したとしても、売買自体がそもそも無効と判断されるので、所有権移転の登記をすることができません。
その結果、後見人の債務不履行責任が問われることになるので、注意が必要です。